
- 書名:湯気を食べる
- 著者:くどうれいん
- 発行所:オレンジページ
- 発行年:2025年
もちろん女性以外のファンも多いのだろうが、くどうれいん の本を薦める女性は多い。薦めるというより<推し>だと公言する感じだ。以前に40代になったばかりのメンバーがRIFFで紹介している。『わたしを空腹にしないほうがいい』というエッセイだ。記事で彼女は「読み進めたら、なんとも美味しい文章!もとい!言葉のセンスやリズム感が素晴らしくて痺れた」と書いた。最近もう一人の知人の40代女性も「読んでるー」とうれしそうに文章<推し>を始めた。
次にくどうれいんが気になったのは2022年に出したエッセー集「虎のたましい人魚の涙」に、個人的に好きな女優の杉咲花が帯を書いていたからだ。くどうれいん は杉咲花の3歳上で、2025年30歳。こうなると年代を超えてファン層というか刺さる人が広がっている感じが見えてくる。
本書を読んで、女優杉咲花があるテレビ番組で、RIFFでも「生まれた時からアルデンテ」「私は散歩とごはんが好き(犬かよ)」を紹介しているフードエッセイストの平野紗季子さんと一緒に岩手・遠野で食べまくりながら語っていた視点や言葉のリズムが、くどうれいんと似ているように思った。熊本在住の料理家・細川亜衣氏に会いにいくドキュメンタリー番組のときも、会いに行ける興奮が素直に画面にでていて、まったく違うシチュエーションなのに、くどうれいんが東京駅大丸へ行くときの興奮と通ずる感じがした。
ちなみに平野紗季子さんは、学生の頃にバイトをして星付きのレストランに一人で行くというような、目的をみつけては必ずそこに到着しようとし続けている人のように見える。役をもらってからどう応えるかという女優とはアプローチが違うのだろう。その旅の二人は双子のようにシンクロしながら明らかに違う道を歩く人だった。
くどうれいんは、水野良樹(いきものがかり)のプロジェクトであるHIROBA公式サイトでの対談でこう話している。
エッセイはどうしても「赤裸々」という言葉と紐付けられることが多いのですが、私は赤裸々に書いたことはなくて。もっと禍々しい部分、もっとうぬぼれている部分もあるけれど、見せたいところしか見せていない。だから、”書く”ということは、編集だと思っています。晒すために書いているわけではなく、むしろ、自分の都合がいいように、編集するために書いているという意識がかなり強いです。
くどうれいん のエッセイは自分を晒して自分や作品を消費させるのではなく、「消費されることへの防衛(水野良樹)」をすることから生まれた小説の一片なのかもしれない。しかし、そうは感じさせない日常の瞬間を切り取る言葉の紡ぎ方がファンの共感を得ているのだろう。
本書『湯気を食べる』は河北新報と料理雑誌オレンジページで連載されたものを中心にまとめたものだ。
自分はこの中で「食べること」について共感したり、考えさせられたりした。
子供の頃母親がまだ料理ができていなにのに食卓に呼ばれることに対して著者はこう書いている。「料理を作ったり、作ってもらうということは、湯気ごと味わうことができるという素晴らしいことだ。湯気ごと味。わたしたちは出来立てのひとくちを味わうために生きているのだから(中略)呼ばれたら一目散に食卓に駆けつけなければならない」
また、「ずぼら」という言葉の抵抗感に対してこう語る。「すべてのご飯は、わたしがわたしをやっていないとたべられないまかないなのだ。わたしはいつもわたしのためにわたしのために働いているのだから、わたしがわたしのたべたいものをつくるとき、それはすべてまかないだ。そう思うと、大きなコック帽を被ったシェフのようでちょっとかっこいい」
安く多めに買うことができたレモンについて「〜きれいに皿を洗って、そこにレモンをすべて置いた。〜ときにわたしはこんなふうに、果物を”食べたい”以上に”置きたい”と思って買うことがある。放っておいたら不安が鎮座してしまいそうな時は、こころの中に、それよりも先に果物をおけばいい」と書いている。
この本は、コンプライアンスなんかで固まっているオジサンたちが読むのがいいかもしれない。
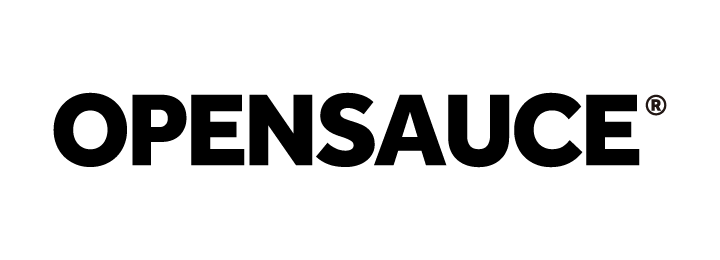



出版にたずさわることから社会に出て、映像も含めた電子メディア、ネットメディア、そして人が集まる店舗もそのひとつとして、さまざまなメディアに関わって来ました。しかしメディアというものは良いものも悪いものも伝達していきます。 そして「食」は最終系で人の原点のメディアだと思います。人と人の間に歴史を伝え、国境や民族を超えた部分を違いも含めて理解することができるのが「食」というメディアです。それは伝達手段であり、情報そのものです。誰かだけの利益のためにあってはいけない、誰もが正しく受け取り理解できなければならないものです。この壮大で終わることのない「食」という情報を実体験を通してどうやって伝えて行くか。新しい視点を持ったクリエーターたちを中心に丁寧にカタチにして行きたいと思います。