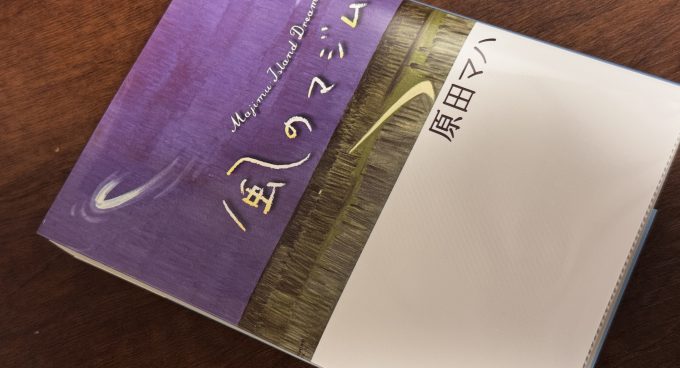
- 書名:風のマジム
- 著者:原田マハ
- 発行所:講談社
- 発行年:2010年 2014年文庫化
本書は伊藤沙莉主演で映画化され、2025年9月12日に劇場公開される。
この本は、沖縄の離島・南大東島で育つサトウキビを使ったラム酒作りを目指す女性の物語。主人公の伊波まじむは、祖母の「いっぺん世間を見て来い」という後押しで東京の大学を卒業したが、東京に出たことにより改めて客観的に沖縄の良さを実感。那覇に戻り通信系IT会社の契約社員として那覇で豆腐屋を営む祖母と母と暮らしている。いつも祖母と⼀緒に通うバーで、ラム酒の魅力に取り憑かれる。
社内ベンチャーコンクールに応募する同僚の手伝いをするうちに、自分でも南大東島産のサトウキビからラム酒を作るという企画で応募することになり、この企画は、やがて家族、会社、島民を巻き込む一大プロジェクトになっていく・・・
これは、日本初の沖縄産アグリコール・ラム酒を造るために企業した南大東島に本社を置くラム酒製造会社『グレイスラム』の金城裕子さんの実話をもとに書かれた小説だ。
アグリコールラムは、サトウキビの搾り汁を原料に作られるラム酒の一種。一般的なラム酒が砂糖の製造過程で出る糖蜜を原料とするのに対し、アグリコール・ラムはサトウキビを絞った新鮮なジュースをそのまま発酵・蒸留して作られる。そのため、サトウキビ本来の風味や香りが強く残り、より個性的で芳醇な味わいが特徴である。絞ったサトウキビのジュースはすぐに使わないとだめになる。モデルとなった金城裕子さんはこの扱いにくく作業に手間がかかるアグリコールのラム酒造りを目指したのだ。
著者、原田マハは商社、森美術館設立準備室、ニューヨーク近代美術館(MoMA)キュレーターとして勤務したのち、フリーのキュレーターとなり、2003年からカルチャーライターとして執筆を開始した。その時にインタビューしたのがまだラム酒造りのスタートにたったばかりの金城裕子さんだった。原田マハは、ラム酒ができたらいつか小説にさせてほしいと金城さんに伝えていたという。
筆者が原田マハの作品を読んだのは画家アンリ・ルソーの「夢」の幻の連作の存在を軸にした『楽園のカンヴァス(2012年山本周五郎賞)』だった。ミステリー作家ではないはずの著者が書いた斬新な絵画ミステリー。実際にMoMAのキュレーターだった彼女ならではの芸術についての描写力と情熱が溢れ、ずっしりと湿度をもった作品だった。
比べてその前に書かれた本作品は、(インタビュー取材から始まったので当然と思うが)ドキュメンタリーをノベライズしたような軽妙さ持った爽快感のある若い女性のドタバタ・サクセスストーリーだ。ただ、沖縄という背景、作中多用される「うちなーぐち(沖縄の方言)」によって、それはただのドタバタではなく人の思いや出会いの素晴らしさがじんわり伝わってくる触れ合いストーリーになっている。
以前に、シングルマザーと漁師たちのサクセスストーリー『ファーストペンギン』を紹介した。方やノンフィクション、本書はフィクションではあるが、どちらも若い女性が未知の領域に挑んで問題を解決していくだが、本書は仕方なく引き受けるではなく、ラム酒が好きという一点で突破していく内容だ。それも、本来あるべきテロワールを生かさなければ意味がないという、ラム酒の姿を真っ直ぐに追い求めビジネス化していくのだ。
われわれのグループにもジンの蒸留所Alembicと日本酒の甍酒蔵という酒造メーカーがある。それぞれ、たった一人の情熱から生まれた企業で、多くの人や地域を巻き込みながら成長し、初リリース間もなく、どちらも国際的な賞を受賞している。本書を読みながら、主人公とそれぞれの代表者と「ああ、こんな気持ちだったのかな」と少し重ねた部分もあった。
ただし、本書の主人公は、酒造りに関してまったくの無知なところからスタートし、冒頭にも書いたが、島を、サトウキビ農家を巻き込み、熱意で醸造家に了承してもらい島に移住させ、事業計画をつくり資金を確保していく。
これらの過程が物語とともに知識として入って来て、酒造りの大変さを再認識することになった。
ただ、酒造りはロマンだけではやれないと言うが、本書を読んで、ロマンがなければぜったいやれないことだということも再認識した。
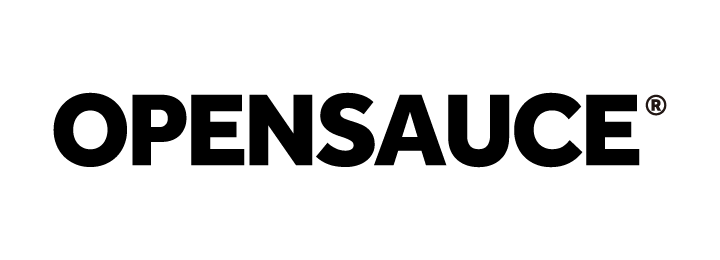



出版にたずさわることから社会に出て、映像も含めた電子メディア、ネットメディア、そして人が集まる店舗もそのひとつとして、さまざまなメディアに関わって来ました。しかしメディアというものは良いものも悪いものも伝達していきます。 そして「食」は最終系で人の原点のメディアだと思います。人と人の間に歴史を伝え、国境や民族を超えた部分を違いも含めて理解することができるのが「食」というメディアです。それは伝達手段であり、情報そのものです。誰かだけの利益のためにあってはいけない、誰もが正しく受け取り理解できなければならないものです。この壮大で終わることのない「食」という情報を実体験を通してどうやって伝えて行くか。新しい視点を持ったクリエーターたちを中心に丁寧にカタチにして行きたいと思います。