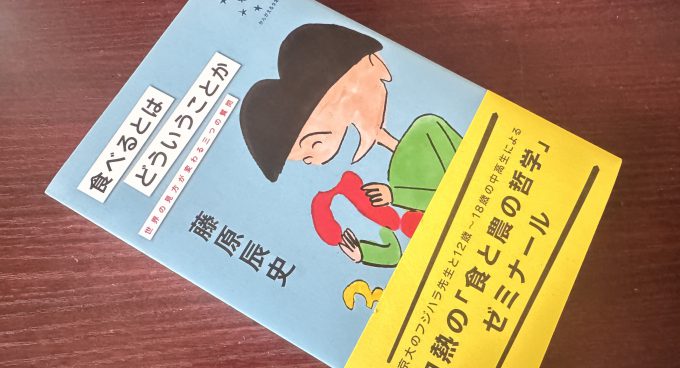
- 書名:食べるとは どういうことか
- 著者:藤原辰史
- 発行所:農文協
- 発行年:2019年
この本は、日本の歴史学者・農業史研究者で農業史・食と農の専門家の京都大学人文科学研究所教授・藤原辰史が12歳から18歳の若者8名と一緒に語った、食と農を考える哲学ゼミナールの記録である。
何について語ったかというと、
- 今まで食べたなかで一番おいしかったものは?
- 「食べる」とはどこまで「食べる」なのか?
- 「食べること」はこれからどうなるのか?
の三つである。この本は難しそうだが、読みやすくわかりやすい。わかりやすいが、答えがあるかと言えばそうでもない。考え始めたら考え続けなければならない。そのことを知るための本である。
著者の藤原辰史は、これは大学で講義するよりもずっと難しいチャレンジっだったという。年齢も知識も興味も違う人たちが集まって、全員が平等に話し合うことができるのか?
しかしその心配は不要なことだった。
そこにいた全員が決まりきった「正しい」という社会通念ではなく、自分自身で感じたり考えたりしたことを話してくれたという。
果たして自分はこれらのことについて、自分は、何か自分なりの意見を述べられるだろうか?うまく話そうということだけでいっぱいになりそうだ。
本書の中身を少し紹介することにしておく。
今まで食べたなかで一番おいしかったものは?
実際に質問するとたった15分では答えられない難しい質問であることがわかったという。理由の一つ目は「おいしい」とは何か、どんな気持ちをあらわす言葉なのか説明しづらいから。二つ目はこれまで食べたものがあまりに多いので選べない。三つ目においしい理由が単純ではないから。4つ目は、自分を公表して発表するとなると気を使うということ。また、それは自分の中にしまっておきたい場合もあるということ。
と言った内容がまず書いてあるのだが、実にその通りだと思う。自分は「何が一番好き?」と言われるのが苦手である。宇宙に放り出された感じになるのだ。アインシュタインとかホーキンスの顔が浮かぶ。
参加した14歳のコータロー。アンケートに「小松菜と油揚げの味噌汁」と付き添いの母親が書いたことを暴露。自分はきゅうりに味噌をつけて食べるとか、シンプルなものが好きだと言う。家になっているもぎたてを食べたくなる。
その答えに対して著者は漫画『美味しんぼ』の例を出す。
フランスに嫌気がさして帰国した美食家のファッションデザイナーを再度フランスへ行きたい気持ちにさせるための食対決。主人公の山岡はおいしいフレンチをだすが、海原雄山は<握り飯とキュウリの糠漬けのまるかじりと水>を出す。デザイナーは、シャキッという歯応えで自分の味覚のルーツを再確認し「根っこ」ができたとフランスに戻る。
15歳の少女、そらは農業大好き少女で自分でトマトを栽培し続けている。いちばんおいしかったものは「自分で種を採って育てたトマト」。交配はしていないけれど、自分で採り続ければ品種改良になると言う。純系淘汰だ。
こんな話も突然始まるのだ。なんの意識もせずにこんな答えを出せるのが少しうらやましくもある。
「食べる」とはどこまで「食べる」なのか?
これはほんとうに哲学。
食べるとは、口に入れて、噛んで、飲み込むことだと思ってはいないかという問いかけ。食べものは胃袋に落ちてしまえば終わりか。小腸までいっても食べものか。微生物に分解されて便になるまでが食べものではないのか?それとも直腸、肛門までか、トイレにおちる寸前までか?食べるということは・・
これも難しい問題。
ここでは、オーガニックな食品を食べている人も、ファスト・フードを食べている人の排泄物は同じ下水処理場にたどり着き、それが地球に循環していくということ。人間にも上水道と下水道のように、その境目があるという話につながっていく。
「どんな権力を持った政治家も、貧しい子どもも、みんなトイレの上では平等」
人生、当たり前だが結構な時間を「食」に費やし、後期になって「食」を考える理念をもった会社から仕事をもらって数年間を過ごしてきた訳だが、真面目にこのことを周りの優秀な食の専門家たちと話したことがない。
とことん考え抜こうとする人はすべて、子どもも大人も哲学者の卵だと著者は言う。
本書で子どもたちの考えとやりとりを読んで、初めて食と農の哲学というものに触れた気がする。
われわれの会社は今、食とは何か、なぜ「食と農」のために集まったかということを、一人ひとり思い返すところに来ているのではないだろうか?
ただ、自分には一つだけ軸がある。オモシロイかどうかである。だから、どんな懸案でもオリジナルな面白さで解決しようと思ってやってきたのである。
本書を読んで、ますますそこに立ち返らなければと感じた。
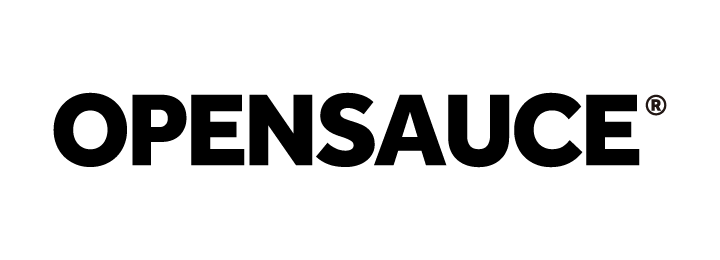



出版にたずさわることから社会に出て、映像も含めた電子メディア、ネットメディア、そして人が集まる店舗もそのひとつとして、さまざまなメディアに関わって来ました。しかしメディアというものは良いものも悪いものも伝達していきます。 そして「食」は最終系で人の原点のメディアだと思います。人と人の間に歴史を伝え、国境や民族を超えた部分を違いも含めて理解することができるのが「食」というメディアです。それは伝達手段であり、情報そのものです。誰かだけの利益のためにあってはいけない、誰もが正しく受け取り理解できなければならないものです。この壮大で終わることのない「食」という情報を実体験を通してどうやって伝えて行くか。新しい視点を持ったクリエーターたちを中心に丁寧にカタチにして行きたいと思います。