
- 書名:おじばさん
- 著者:ひぐちきょうこ
- 発行所:さくら社
- 発行年:2024年
ひぐちきょうこ(樋口匡子)さんは埼玉県生まれ金沢市在住の画家・イラストレーター。かつて絵画教室で子ども達と過ごした経験から生まれ、初めて出版した絵本がこの「おじばさん」だ。
10歳の少女が父親と自分のことを日記のように語っていく、やわらかくもなんとも言えない切なさが漂う日常。
「わたしのパパはかわってる。おじさんなのにおばさんみたい。だからわたしはおじばさんってよんでます。だれにもいったことがない、わたしだけのよびなです。」
「おじばさん」はコックさんだ。仕入れから料理までランチ、ディナーと一人でこなす。店が小さいのでウェイターは夜だけ居る。少女は聞くことなく家の経済がどんな状況かをなんとなく感じている。少女は習い事のない学校帰り、レストランに寄り夜ご飯を食べ、店の隅で宿題をする。そしてシングルファザーであることは後半でわかってくる。




この絵本は、誰もが経験したことのあるポツンと自分が存在しているような少し切ない感じを認識し始める思春期の頃を思い起こさせる。しかし、父親の「おじばさん」や、その仕事の間、少女を見ていてくれるおばあちゃんの愛情が彼女を常に包んでいることも伝わってくる。具体的な言葉では書かれていないが、少女が淡々と語る生活行動から見える。
「おじばさんはおみせがやすみの火よう日、ひとりでスポーツジムにいきます。わたしはがっこうがおやすみの日よう日、ひとりでとしょかんにいきます」
ひぐちきょうこさんは、あるインタビューで「(この絵本を読んで)「さみしさを口に出せないでいる子に、『自分だけじゃないんだ』と思ってもらえたら」と話していた。


単純に「さみしさ」という括りの話ではないが、自分はこども食堂の子どもたちのこと(様々であろう生活環境のこと)を漠然と想像することがよくある。早く父を亡くし、歳の離れた兄は家を出て地方の学校の寮に入ったため、二人だけの母子家庭のような生活をしていたからだろうか。
テレビの取材でよく見るのは子供たちが元気におかわりしている風景や仕事が忙しい親と子でやってきて食堂の存在に感謝している映像だ。テレビはあえて心の中に踏み込むことは避けているのだろう。取材に答える子供たちも大人の期待に応えるようなコメントを残してくれる。こう感じるのはこちらの思い込みも強いようにも思いはするのだが。
認定NPO法人全国こども食堂支援センター『むすびえ』の調べによると、2024年12月までで開設されている石川県のこども食堂は98ヶ所となった。能登半島地震の影響もあるかと思うが、2023年度の46ヶ所から倍増している。全国のこども食堂は1万867ヶ所となり1万ヶ所を超えてしまった。そして参加者数は年間延1885万人だ。
日々こども食堂の運営に携わっている方々には頭が下がる思いで、食事を提供するだけでも手一杯だと思う。それでも「食べること」ということは何かをさまざまな角度から大人が考えなければならないところまで来ているように思う。
この絵本の少女が心の中だけでシングルファザーの父親を「おじばさん」と呼んでいるという話しからそんなことを考えた。
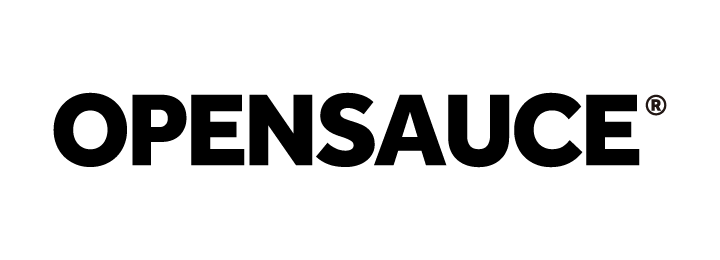



出版にたずさわることから社会に出て、映像も含めた電子メディア、ネットメディア、そして人が集まる店舗もそのひとつとして、さまざまなメディアに関わって来ました。しかしメディアというものは良いものも悪いものも伝達していきます。 そして「食」は最終系で人の原点のメディアだと思います。人と人の間に歴史を伝え、国境や民族を超えた部分を違いも含めて理解することができるのが「食」というメディアです。それは伝達手段であり、情報そのものです。誰かだけの利益のためにあってはいけない、誰もが正しく受け取り理解できなければならないものです。この壮大で終わることのない「食」という情報を実体験を通してどうやって伝えて行くか。新しい視点を持ったクリエーターたちを中心に丁寧にカタチにして行きたいと思います。