
- 書名:やさいたちのうた
- 著者:詩・藤富保男 絵・谷口宏樹
- 発行所:福音館書館
- 発行年:2016年
2歳のこどもに読み聞かせたら、きゃっきゃと喜ぶのか混乱するのかわからないが、大人になっても頭の中のシワにこびりついていそうな詩の絵本である。そして楽しい(少なくても充分おとなになった自分にも)。幼児が嫌いな野菜が好きになるかどうかは別として。
藤富保男は(1928年8月15日 – 2017年9月1日)は、東京府小石川区(現・文京区)生まれの詩人だ。詩においてもユーモラスな表現の作風で「視覚と音律から日常の言語を再構築する独特な詩法を持っていた。
「アイロニー」という言葉がある。藤富保男を評するときによく使われる。
例えば「彼にとっては、絵を描くことも詩を書くことにほかならない(自身の描いた線描画展において)。あふれるユーモアとアイロニー、そして、ダンディズム。観念や論理に縛られることなく、自由に展開される藤冨ワールドは、笑いを誘い、現実を異化する」とか「単純に見えて、普通とは違う。その違いは、アイロニーを含み、見る者を詩の世界に誘う」などのように。
「アイロニー」は、日本語の会話や文章の中でも「皮肉」という意味で嘲笑したり批判したりする時に使われることが多いと思うけれど(ちなみに自分はなんだか使うのが恥ずかしいので使ったことはない)、「アイロニー」と「皮肉」はニュアンスが異なる。
「皮肉」はストレートに相手を批判したり、少し凹ませたり傷つけたりするニュアンスだが、「アイロニー」は自分が思うことと反対のことを敢えて言うことで笑いを取ったり、相手に何かを気づかせる効果をもった内容をいうのだと思う。
ダダ、シュルレアリスムの影響を受け詩作をスタートした異端の詩人、藤冨保男はイメージとは何かを考えたとき、イメージとは映像であり、詩のなかに映像を立ち上げなければならない」と考えたという。
また、「なさそうであることと、ありそうでないことは違う」と語り、そして、「ありそうでないこと」を考え続けてきたのだという。
そんな詩人が「やさいたち」を思うとこんな「うた」になるのだなあ。




藤冨保男は線描画も描くのだけれど、この本の絵は谷口宏樹氏が担当している。谷口宏樹さんは同年代で若い頃に何度かお会いしている。また、ポップカルチャーと云われる作品が取り沙汰されていた時代に、その不思議な淡さを持つイラストレーションも使用させてもらった。
1928年生まれの藤冨保男はこの本が出版された翌年の2017年に亡くなっている。そして、1957年生まれの谷口宏樹氏も2021年に亡くなった。
二人は年代が違うのだが、この本を残してくれたことに感謝する。
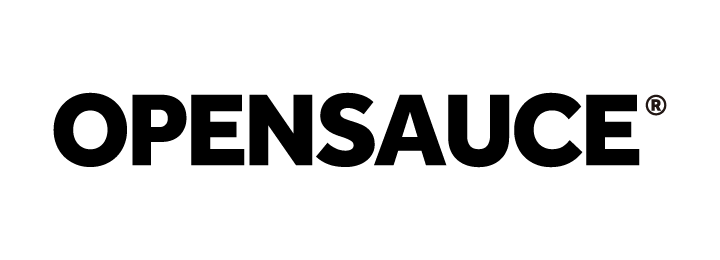



出版にたずさわることから社会に出て、映像も含めた電子メディア、ネットメディア、そして人が集まる店舗もそのひとつとして、さまざまなメディアに関わって来ました。しかしメディアというものは良いものも悪いものも伝達していきます。 そして「食」は最終系で人の原点のメディアだと思います。人と人の間に歴史を伝え、国境や民族を超えた部分を違いも含めて理解することができるのが「食」というメディアです。それは伝達手段であり、情報そのものです。誰かだけの利益のためにあってはいけない、誰もが正しく受け取り理解できなければならないものです。この壮大で終わることのない「食」という情報を実体験を通してどうやって伝えて行くか。新しい視点を持ったクリエーターたちを中心に丁寧にカタチにして行きたいと思います。