
- 書名:作家のまんぷく帖
- 著者:大本泉
- 発行所:平凡社
- 発行年:2018年
これまでRIFFにおいて「文士の食卓」「文士料理入門」「もの食う話」「吉田健一 酒肴酒」「椎名誠・選 麺と日本人」など作家と食にまつわる本を紹介してきた。今回紹介する「作家のまんぷく帖」に登場する総勢22人の作家たちとだいぶ重なっているが、この本は “この食にしてこの人あり” と納得させる、もしくは本当の人柄を見せてくれる。
さて、文学史に名前を残す作家たちがどんな食生活をしていたかに興味を持つ人はどのくらいいるのだろう。少なくても自分は興味があってこの本を入手したのだけれど、面と向かって他人に奨めるには少し気がひける。
特に明治生まれで大正、昭和に活躍した文豪と呼ばれる作家たちについては、当然のごとくすべてを読破したことなぞなく、その人物像については関川夏央 原作・谷口ジロー 画「坊ちゃんの時代」という漫画のシリーズで知ったというのが正しい。
この程度の浅い人間が何をか言わんや、と思われること必至だ。しかし「坊ちゃんの時代」で学んだ文士たちの才能と人柄と時代背景、そして生活に大いに興味を持ったことは確かだ。(と、作品はほとんど読んでないに近いけど面白いから言いたいんだよ、という言い訳をしている)
さて、金沢出身の近代作家3人といえば室生犀星、徳田秋声そして泉鏡花だ。この本では泉鏡花が取り上げられている。それも病的なほどの潔癖症で「食べるのがこわかった」人物としてだ。
鏡花は刺身などの生ものは見るのもいやで、銀座木村屋のアンパンの餡を抜いたようなパンが好物だった。そのパンを指でつまんで食べ、指が接していた部分だけをポイと捨てていた。
酒に関してはぐらぐらにつけた熱燗を飲んだ。
しかし、神楽坂時代には執筆前の夜食として「大どんぶりに、菜漬けをいっぱい、それに烏賊の生漬けという、不衛生で消化の悪そうなもののおかずで大飯をバクバク食べていた」ともある。
それでも酒はグラグラ煮燗して煮沸消毒をして飲んだ。夜食の後の林檎は十二分に手を洗った夫人が林檎の実に手が触れないように器用に剥き、鏡花は林檎の頭とお尻のところを親指と人差し指で持ち、横齧りをした。指の触れたところは、これまた捨てていたという。
鏡花には「鏡花世界」らしからぬハイカラな面もあったらしい。クリスティーの帽子、クロノスの歯磨き粉そして葉巻と紙巻、湿布薬や汗疹用の亜鉛化澱粉も外国製だった。葡萄酒、ブランデー、ウイスキー、ベルモットにも好みがあったという。
著者、大本泉は「鏡花の描く女性には日本人でも外国人でもあるような、母親のような少女、聖女のような妖婦といった多面性を持つ魅力的な人物が多い」「相反するかのような観音力と鬼神力という二つの超自然力を信じて文学に形象化したように、実生活における鏡花は、江戸の粋な食べ物と西洋の両方を好むこだわりがあったようだ」と書いている。

泉鏡花に関するエピソードはもちろんもっと多く書かれているが、このように著者は「赤貝がのどに張り付いて絶命した久保田万太郎」「揚げ物火加減に厳格なこだわりを見せた獅子文六」「胃痛を抱えながら酒と薬が手放せなかった坂口安吾」など、食べ物から作家の素顔と本質を分析していく。
取り上げられた主な作家は他に、樋口一葉、斎藤茂吉、高村光太郎、魯山人、平塚らいてう、石川啄木、内田百閒、佐藤春夫、江戸川乱歩、宇野千代、小林秀雄、森茉莉、幸田文、中原中也、武田百合子、山口瞳、藤沢周平。
それにしても、個人的に村上春樹や東野圭吾の食生活に興味が湧かないのはなぜだろう?
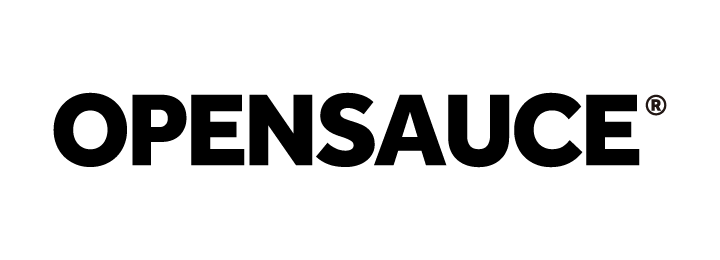



出版にたずさわることから社会に出て、映像も含めた電子メディア、ネットメディア、そして人が集まる店舗もそのひとつとして、さまざまなメディアに関わって来ました。しかしメディアというものは良いものも悪いものも伝達していきます。 そして「食」は最終系で人の原点のメディアだと思います。人と人の間に歴史を伝え、国境や民族を超えた部分を違いも含めて理解することができるのが「食」というメディアです。それは伝達手段であり、情報そのものです。誰かだけの利益のためにあってはいけない、誰もが正しく受け取り理解できなければならないものです。この壮大で終わることのない「食」という情報を実体験を通してどうやって伝えて行くか。新しい視点を持ったクリエーターたちを中心に丁寧にカタチにして行きたいと思います。