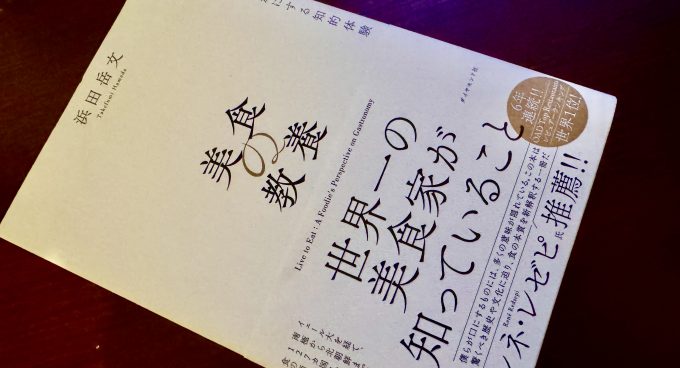
- 書名:「美食の教養」
- 著者:浜田岳文
- 発行所:ダイヤモンド社
- 発行年:2024年
著者・浜田岳文(敬称略・以下浜田)は「グルマン」つまり「美食家」であり、世界中で食べ歩く「フーディー」である。それも世界一の。
美食家は伝統的な高級料理や、最高級の食材を求めるイメージが強い場合があるが、フーディとは美食を追求するライフスタイルを持つ人を指し、食を愛し探求する姿勢が強調される。また、フーディとは、単に「食べる」だけでなく、食を通して人生を豊かにしようとする人々を指す言葉でもある。また、料理の背景にある文化やシェフのクリエイティビティを深く理解しようとしている。
浜田は、自身が見つけ出した「美食の定義」をしっかりと持ち、想像を超える数の料理に向かい合い続けている世界一の美食家であり、フーディーと言える。
そしてその明確な定義を持った浜田が、広くグルメ入門書としてまとめたものが本書だ。入門書ではあるのだが、実は食と食に関わる者への警鐘本であると自分は感じている。食について、もっと多くの問題に気づかなければならないと言っているように感じるからだ。
1974年生まれの浜田は、イェール大学(NY)在学中に学生寮の食事の不味さから逃れるべくニューヨークを中心に食べ歩きを開始。その後、本格的に美食を追求するためのパリに留学。金融機関を経て、さらに南極から北朝鮮まで約127カ国を踏破。2017年の「世界のベストラン50」の全店を制覇。
現在も1年のうち海外で5ヶ月、東京で3ヶ月、地方で4ヶ月、食べる、食べる、食べる。
そして浜田は「OAD世界のトップレストラン」のレビュアーランキングで2018年から6年間連続第1位の位置を保持し、食や旅に関する情報をさまざまなメディアで発信し、世界のトップシェフたちとの交流も続いている。
料理人との交流ということでは、自身が「食」について発信する『UMAMIHOLIC』というYouTubeチャンネル があり、世界No.1の浜田だからこそ聞き出せる、料理人との対談を公開している。ちなみにShortでは、365日外食する浜田の毎日の食事を公開中だ。
浜田には犠牲?にしていることも多いと自身で言っている。すべてのお金と時間は、食と旅のために使い、それ以外には全くお金を使わない(使えない)と、あるインタビューで答えている。また、50歳を迎えて独身の浜田。年間5ヶ月は海外生活という現在のライフスタイルを続けようとする限り、結婚生活や、子育てをすることは難しいと考えている。
また、浜田は食の中でも外食に興味を持っていることを強調する。「食を通して料理人というクリエイターの作品を鑑賞し享受することを目的にしている」のだ。
ほんとうに犠牲と言っていいのかどうかはわからないが、こういうライフスタイルを貫くことで世界一のフーディーとして名を馳せているのは確かだ。
冒頭で浜田は、食事には3つの段階があり、第一は「栄養摂取」、第二は「うまい」、第三は「美味しい」だとし、自分はどんな食べ方を選ぶのか、何に生きがいを求めるか?食事はその人の生き方も表すと書いている。そして、本書を<これは、食通、グルメともてはやされたい人のガイドブックでは決してない>とし、本書の教養を身につければ、美食に対する誤解が解け、知的体験としての食事が待っている、と言う。
そして、
美食=高級ではない。美食は、文化を丸ごと食べること。いわば、食の文化人類学。
とした。
浜田は「単にものをたべるのではなく、ものの背景にある歴史だったり、文化だったり、そういうものを感じながらいただきたい」と思っている。
美食の再定義として浜田は、
文化的に食べる。「うまい」だけではない「美味しい」を探求する。
と書いている。
『Frau』のWEBマガジンのインタビューでは美食の評価についてこう話している。(以下2024.08.10の記事より抜粋)
“どうやって美食を評価するのか。僕が心がけているのは、2点です。
まず1点目は、その料理が「どれだけ考え抜かれているか」です。 これはあくまで僕の独自の基準でしかありませんが、僕が評価するのは、徹底的に考え抜かれている料理なのです”
“世の中には、昔ながらの伝統の味を受け継いでいます、という店がたくさんあります。それはそれで素晴らしいのですが、受け継がれたレシピをそのまま再現しているだけなのか、それともそれをベースにより良くしようとしているかでは、雲泥の差があります”
数千円の料理でも、考え抜かれているものはわかります。〜 略 〜 一方、5万円でも考えられていない料理もある。その意味では、料理の深さは価格とは関係ないことが多いのです。
この本はNomaのシェフ、レネ・レゼピ氏が本書の推薦文で書いているように「僕らが口にするものには、多くの意味が隠れている。この本は驚くべき歴史や文化に迫り、食の本質を新解釈する」一冊である。
そして本書は以下のようにまとめられている。
・人生を豊かにする「美食の思考法」
・美味しさに出会う「美食入門」
・食から国の素顔が見えてくる「世界の料理総まとめ」
・美食家なら知っておきたい「グルメ新常識」
・美食を生み出す「一流料理人の仕事」
・私たちは何をどう食べるのか「美食の未来予測」
すべて浜田自身の足と目と舌で分析し、発見した内容である。
グルメ入門書である本書を読んでいると、各章ごとに<食べるということ>をなん度も考えさせられる。いかに自分が考えていなかったが明確になっていくので、食の仕事についている者としては恥いってしまう。もちろん、著者の食べることへの真理にたいする共感の裏返しなのだが。
本書では各章の間の「いい客になるための美食講座」というコラムを設け、テーブルマナーや礼儀、オーダーの仕方や常連について書いている。
これは浜田の「ここ5年ほど、特に若い世代で食べ歩きを趣味とするフーディーが増えているように感じます。ただ、中には誘われた会に行ったら嫌な思いをしたりとか、幹事として誘ったらドタキャンされた、などの残念な話も聞こえてきます。 また、飲食店側からも、食事会にマナーを守れない人が紛れ込んでいて困惑した、といった話を聞くことも増えました(Foodies Primeプレスリリースより) 」という状況から書かれているように思った。
浜田は2023年6月、予約の取れない人気飲食店に、行きたい人と一緒に行けるフーディー特化型SNS「Foodies Prime(フーディーズ プライム)」顧問に就任している。このSNSでは審査で入会を認め、「嗜好の合うメンバーの募集」「キャンセル発生による参加者の再募集」「フーディー同士の飲食に関する情報共有」等をサポートするサービスを提供している。
追記:2025年11月、浜田岳文はThe World’s 50 Best Restaurants および Asia’s 50 Best Restaurants における日本の評議委員長に就任した。。
本書とともに浜田岳文に関連するサイトを覗いてみることをお勧めする。
https://www.instagram.com/takefumi.hamada/
https://www.youtube.com/@UMAMIHOLIC
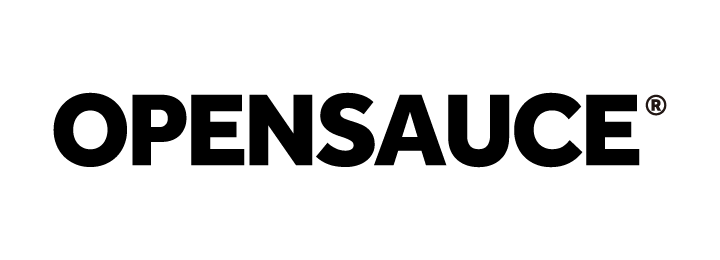



出版にたずさわることから社会に出て、映像も含めた電子メディア、ネットメディア、そして人が集まる店舗もそのひとつとして、さまざまなメディアに関わって来ました。しかしメディアというものは良いものも悪いものも伝達していきます。 そして「食」は最終系で人の原点のメディアだと思います。人と人の間に歴史を伝え、国境や民族を超えた部分を違いも含めて理解することができるのが「食」というメディアです。それは伝達手段であり、情報そのものです。誰かだけの利益のためにあってはいけない、誰もが正しく受け取り理解できなければならないものです。この壮大で終わることのない「食」という情報を実体験を通してどうやって伝えて行くか。新しい視点を持ったクリエーターたちを中心に丁寧にカタチにして行きたいと思います。